 先ほど、NTT労組コミュニケーションズ本部松田副委員長、仁藤総務部長が事務所にいらっしゃいました!
先ほど、NTT労組コミュニケーションズ本部松田副委員長、仁藤総務部長が事務所にいらっしゃいました!
NTTコミュニケーションズシャイニングアークスの2014—2015年ファーストステージの試合日程入りポスターをお持ち頂きました。
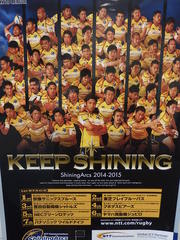
今年は監督もかわり、第2ndステージ、グループAを目標に頑張っているそうです!
優勝めざしてがんばって下さい!!
 先ほど、NTT労組コミュニケーションズ本部松田副委員長、仁藤総務部長が事務所にいらっしゃいました!
先ほど、NTT労組コミュニケーションズ本部松田副委員長、仁藤総務部長が事務所にいらっしゃいました!
NTTコミュニケーションズシャイニングアークスの2014—2015年ファーストステージの試合日程入りポスターをお持ち頂きました。
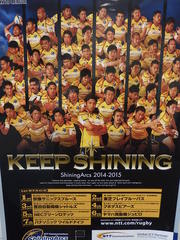
今年は監督もかわり、第2ndステージ、グループAを目標に頑張っているそうです!
優勝めざしてがんばって下さい!!
本日(7月22日)、私も呼びかけ人となっている「平和と安定のための安全保障を考える連絡会」の主催で『集団的自衛権行使容認に反対する連続勉強会』の第2回目を開催しました。

講師は、「明日の自由を守る若手弁護士の会(通称、あすわか)」の早田 由布子(はやたゆふこ)事務局長。「法律家から見た様々な課題と今後の運動の展開」というテーマで約20分、ご講演いただき、残りの時間で参加者の皆さんと意見交換させていただきました。
早田さんが活動されている「あすわか」は、2012年4月に発表された「自民党改憲草案」に反対の声を上げるため、登録15年以下の若手弁護士有志の皆さんが2013年1月に立ち上げた任意団体で、現在、全国で約330名の若手弁護士が参加しているそうです。改憲や護憲ではなく、「知憲」を掲げて、「まず憲法を知ろう」をテーマに、法律を学んだことのない方々にもわかりやすく憲法の知識を得てもらうための幅広い活動を行っています。今回の安倍政権の解釈改憲による集団的自衛権の行使容認問題についても、大変積極的に問題提起されているので、今回お話を聞く機会を設定したというわけです。

早田さんは、今回閣議決定された自衛権発動の新三要件が、地理的範囲もない非常に曖昧な内容で、限定容認どころか内閣に対する白紙委任となってしまっていること。また、特定秘密保護法のもとでは、国会議員であってもきわめて限定的な場合でしか情報が開示されないため、自衛権行使が新三要件をみたすか否かの実質的判断ができず、国会の事前もしくは事後承認の有効性が疑われること。さらには、閣議決定されたことで、中学高校用教科書で集団的自衛権についての記述がある11社(中学3社、高校8社)のうち、8社が記述内容の訂正申請を検討するなど、集団的自衛権行使の既成事実化がどんどん進んでいく危険性があることなど、大変わかりやすく、かつ端的に、この問題の重大性をご指摘いただきました。

これから、自衛隊法等、個別法の改正の分野に入っていくと、国民にとって議論がますます見えづらくなるので、今、世論を盛り上げることが絶対条件で、そのために「わすわか」では、安倍内閣に即時反論をするために、1時間以内にわかりやすい資料を発表できるよう常に準備していること。主権者意識の向上のために「憲法カフェ」のような草の根学習会を全国で展開している等、運動の展開についても、今後の私たちの活動に大変参考になるお話を聞くことができました。
今日も暑い中、足を運んでいただいた多くの友好団体の皆さんともしっかり連携しながら、さらに国民の皆さんに、この問題の理解が深まるよう活動の情報発信を強化していきますので、皆さまの引き続きのフォローをよろしくお願いします。
7月18日(金)の午前中、私が国会議員になる前に8年余り勤務していた国際労働機関(ILO)で現在、活躍してくれている日本人専門家3名が国会事務所を尋ねてきてくれました。皆さん、休暇等で帰国中で、何かとお忙しい中だったのですが、私が事務局長を務めているILO活動推進議員連盟(以下、ILO議連)との交流と、日本の国会議員として活動しているかつての同僚を激励するという意味合いを兼ねて、わざわざ時間を割いて来てくれたのです。嬉しいですね!

(右から、小笠原さん、坂本さん、私、野口さん、そして駐日事務所の上村さん)
野口好恵さんは、私が1998年に初めてILO総会に出席して、第182号条約(最悪の形態の児童労働即時撤廃条約)の策定議論に関わったときに初めてお会いしているので、もう随分前からの知り合いです。長年、IPECという児童労働撲滅プログラムに関わってきておられるので、NTT労組をはじめ、児童労働問題に取り組んでいる日本の労働界にも知り合いはたくさんおられるはず。現在は、ジュネーブ本部で上級法務官として活躍されています。
坂本明子さんは、実は私と入れ違いで、ILOのマニラ事務所に赴任された方。私がいた頃、マニラ事務所はサブ地域事務所で、フィリピン、インドネシアに加え、フィジーやサモアなどの南太平洋諸島の国々も管轄していたのですが、その後の地域組織再編で、マニラ事務所はフィリピン事務所となり、フィリピン国内での活動に集中しています。かつては5人もいた日本人も、今は坂本さんだけ。今は長期休暇中とのことでしたが、マニラに戻ったらまた活躍してくれることと思います。
そして小笠原稔さんは、アフリカ・ケニアのナイロビ事務所を拠点に活動中です。お話しを聞いたら、もう5年以上、ケニアに駐在しておられるとか。しかも今、アフリカのILO関連事務所で日本人は小笠原さんだけなんだそうです。いや、そりゃビックリ。なかなか厳しい環境ではありますが、ぜひ小笠原さんには引き続き頑張っていただきたいですね。
私もお三方から久し振りにILOの状況をお聞きして、大変有意義でしたし、ILO勤務時代がとっても懐かしく感じられました。今後、ILO議連としても日本人スタッフの活動を支援していきたいと思いますし、何と言っても、日本人の数をもっと増やしていけるように応援していきたいと思います。我こそはと思っておられる方、ぜひどんどん手を挙げて下さいね!
7月14日に開催した第1回「集団的自衛権の行使容認に反対する勉強会」、すでにこのブログでも報告済みですが、議事録が出来ているので掲載しておきます。「分かりやすい!」と評判です。ぜひご一読を!
ちなみに、7月22日に第2回勉強会をやります! 詳細はFacebookページの案内をご覧下さい!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「第一回 集団的自衛権行使容認に反対する勉強会」講演録
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
○講演日時:平成26年7月14日17時~
○講師:半田滋 氏(東京新聞論説兼編集委員)
○講演録:
東京新聞の半田です。
7月1日に閣議決定がなされ、直ちに記者会見が行われました。安保法制懇の答申後の5月15日の会見と同じようにウソをついているなと思うところが多々あります。今回は、7月1日の安倍首相の言葉を、実は違うのではないのかと言うことについて述べさせていただきます。
1.紛争国から日本人が米国艦船で避難するばあい、その米国艦船を日本の自衛艦が警護する事案について
紛争国から帰国する母子が米国の輸送艦に乗って避難し、警護の依頼が来ているのに今の憲法解釈ではできないと赤い大きな×が打ってあった。しかし、本当にこのような日本人親子がいるのだろうか。
既に国会ではもう議論になっているが、これを規定しているのが日米ガイドラインである。1993年に、北朝鮮がNPT脱退を表明したあと、アメリカが北朝鮮の空爆を計画した。このときに我が国政府は、集団的自衛権の行使は認められていないので、アメリカが期待するような対米支援は何も出来ないという回答をし、日米の関係が多少ぎくしゃくした。
それをうけて翌年の日米ガイドラインの改訂にいたるが、ガイドラインの周辺事態というのは、朝鮮半島で戦争が起こったときに自衛隊が支援をするという趣旨の内容が書いてある。その周辺事態の中で、日本人の母子のような非戦闘員を第三国から安全地域に退避させる必要のある場合には、おのおの国が責任を有するとされている。
すなわち日本政府は日本国民を、アメリカ政府はアメリカ国民を運ぶと書いてある。続く文章で、言い訳がましく余裕があれば日本人を運ぶことも考えても良いとなっているが、肝心なのは「おのおのの国が責任を持つ」とのくだり。前後するが「日米防衛協力指針委員会」で、自民党の中谷元衆議院議員が、(我が国避難民の移送について)最終的にはアメリカに断られたと国会の中で発言もしている。
そもそも安倍総理が熱弁をふるったような、米国艦船に乗って運ばれる日本人はいない。いたとしても極めて限定的であって、それを中心に押し立てて集団的自衛権の行使をしなければいけないという議論は筋違いである。
少し考えて見ればわかるが、アメリカの船を警護出来るくらいなら、なんで自衛隊の艦艇や航空機で、日本国民を直接運ばないのかと疑問である。
おのおのの国民を運ぶとういのが元々のガイドラインの精神であるので、この話自体が話にならない。
2.自衛隊の機雷除去にみるような戦闘行為(武力行使)への参加
本日の国会審議でもあったが、そもそも安倍総理の頭の中には多国籍軍のホルムズ海峡における機雷の除去の事があると思う。
機雷の敷設自体が武力行使であり、これを除去する行為自体が武力行使になる。首相は「消極的な武力行使」とは言うが、要は武力行使なので、「戦闘に参加することは決して無い」と言いながら(武力行使となる)戦闘に参加すると言っている。例えばイラク戦争は、国際法的な位置付けはどうかと言えば極めて曖昧で、あれがアメリカの先制的自衛権の行使なのか、或いは国連の安全保障措置としての武力行使だったのかというと非常にはっきりしない。
少なくともアメリカ政府は、パキスタン戦争と違って、国連安保理に個別的自衛権で戦争を始めたとは報告していない。違法な戦争にとどまっている。ただし、本格的な戦闘が終結したあと、ブッシュ大統領が宣言した2003年5月以降は、国連安保理の措置として、いわゆる多国籍軍ができたので、それ以降は国連の安全保障措置といえる。
我が国政府、2003年にイラク特措法を作った。小泉首相は、「日米同盟、信頼関係の構築について、これからも重要なことだと認識しております」と述べて自衛隊のイラク派遣を決め、翌年の一月に自衛隊がイラクのサマワと隣国クウェートに自衛隊が送り込まれた。憲法の規定で人道支援にとどまった。
しかし、安倍首相は日米同盟を強化するとして、集団的自衛権の行使を解禁したのだから、論理の帰結として当然、次は自衛隊が武力行使を目的としてイラク戦争のような場面に送りこまれることになるだろう。首相は「戦闘に参加するようなことは、これからも決してない」と言っているが、これまでの日本政府のアメリカ政府とのつきあい方を見れば、断ることができるはずがない。今後、戦闘部隊も送り込むのではないかと指摘せざるを得ない。
3.安倍首相の言う限定的な武力行使の結果
安倍首相の発言によれば、「他国を守る為に日本が戦争にまきこまれるという誤解があるか。あり得ない」と発言している。ここで「あり得ない」といっているので、「限定的」な集団的自衛権行使した後の、やり返されたときの対処を、政府は何も考えていないと判断せざるを得ない。
昨年3月17日の北朝鮮の労働新聞にもこう掲載された。「朝鮮半島で戦争の火花が散り、自衛隊が介入しても日本が無事だと思いたいならば、それより大きな誤りは無い。」すなわち、限定的であれ、有事に参加すれば手痛いしっぺ返しが帰ってくる。朝鮮労働党はそう言っている。具体的にどういうことが起こるのか。
1993年に北朝鮮がNPT脱退の際、我が国政府は、戦争になるかもしれないと、関係省庁が集まり起こりうる事態について検討した。現在の統合幕僚監部が、対処計画、マル秘計画を策定したが、そのさい起こりうる事態として北朝鮮が軽歩兵師団およそ1万人程度は日本に差し向けることができると推定された。
彼らがどのような手段で日本に来るかは特定していないが、彼らが行うことは、重要施設や港湾などの破壊活動である。では重要施設とは何かと言えば、国会などの政府中枢機関、港湾や原子力発電所、発電所、水道などインフラ施設を破壊する。日本の港には、水中聴音機が張り巡らされていて、他国の潜水艦が入れないように監視されているが、私が知っている位ですから、北朝鮮は、そういう施設も破壊することが予想される。
弾道ミサイルの保有数は93年当時とは比べものにならない。米国防総省は昨年発表した報告書で発射機は350基としている。弾頭はもっと多いだろう。「限定容認」というのはこちらの立場で、相手がそれで許してくれるかどうかは、相手が考えることだ。日本が受ける被害は、限定容認だろうが、本格的な集団自衛権の行使だろうが、変わりない。
4.安倍首相の言う「積極的平和主義」は、「平和主義」の部分より、「積極的」の部分に重きが置かれている
我が国は、平和国家としての道を歩んできた。自衛隊の創設以来、日本国憲法の武力行使、戦争放棄を定めた上での活動が連綿と行われてきたわけで、今回、他国の防衛の為に武力を行使するのだというのは、まったく今までの政府の見解とは次元を異にしていると言える。安倍首相の言う「積極的平和主義」ですが、「積極的」なところに重点があって、平和の為には武力行使もいとわずというのが、安倍首相の考え方だ。
我が国は戦後一貫して平和国家として武力とは無縁な形で国際貢献を続けてきた。見直されようとしているODA大綱でも、今後は軍と援助が使われるようになる。すでに武器輸出三原則はなくなり、武器輸出を認める防衛移転装備三原則にかわった。
そうなるとこれまで国際社会の日本を見る目が違ってくるのではないか。国際軍縮会議などで、武器輸出をしないことでとれたイニシアチブがこれからは取れなくなる。アメリカやロシアと同一視されることになる。また、イラク派遣では人道支援にとどまったにも課下保らず、アルカイダ系武装集団から敵視をされ、昨年のアルジェリアでの日揮の事件では、日本人が探され、10名が亡くなる悲劇も起きている。今後海外で活躍する日本人が攻撃されることが出てくる。
5.結びとして今回の「新三要件」がもたらす帰結
本日の国会論戦でもそうだと思ったが、新三要件は、法律的な文章としてみれば、実はものすごく歯止めが効いている。
これは「武力攻撃が発生」し、「これにより我が国の存立が脅かされ」、なおかつ「国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される」と明白な危険がある、と三重に縛りが効いている。内閣法制局が見て、我が国の憲法にも反しないと判断しているわけだから、この通り読んでいくと、安保法制懇や与党協議で話されてきたような集団的自衛権行使の事例は何一つ出来ないことになる。
公明党の山口代表は「今までと変わりません」と言うが、この文章をみる限りでは、集団的自衛権について、その主張は正しいと思う。しかし、安倍首相は「集団的自衛権が行使できるようになった」と言っている。
ではどうなるか。最終的には首相の総合的な判断こそが前面に出てくるのではないか。来年の通常国会で予定される自衛隊法などの法改正は、「直接侵略、間接侵略に対して武力行使出来る」という専守防衛を踏み越え、「他国の防衛の為に自衛隊を活用する」といったはっきりとした書き方になるだろう。
しかし、それでは内閣法制局が憲法に違反するといって法制局を通さない事態も出てくる。通らなければ改正案を国会提出できないので、集団的自衛権の発動は出来なくなるから、改正案も今回の閣議決定のように曖昧となってしまうおそれがある。
そうすると最後は時の政権の判断、さじ加減で自衛隊が武力行使をすれば良いとなる。日本版NSCもできて、首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣の4人で、密室で協議し、アメリカ等から受けた自衛隊の派遣要請を、全てを特定機密にして囲い込んだうえで、いつ、どこで、何をやるかと言うことを一切国会にも諮らず、国民にも示さないままに自衛隊を送り出してしまう。「原則」事前承認ですから、「時間が無かった」で通る。その後に、自衛隊が戦争をやっていることがわかる。こういったことが起こるのではないか。
曖昧にしてあって、「私が最高責任者である。」と言っていた事が現実になるのではないか。やはり極めて危険な局面を迎えたと考える。
(了)
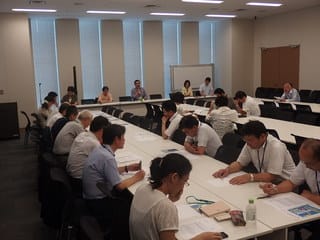
7月14日(月)、民主党の有志議員で立ち上げた「平和と安定のための安全保障を考える連絡会」の主催で、「第1回 集団的自衛権行使容認に反対する勉強会」を開催しました。会場には、連絡会の賛同議員の他、民主党支援組織からも多くの方々が詰めかけて下さって、この日の講師、東京新聞論説委員の半田滋さんの話にみんなで聞き入りました。
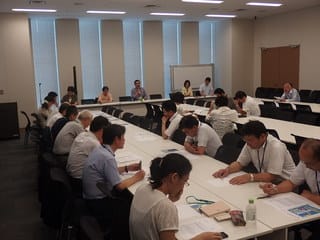
皆さんもご存じの通り、去る7月1日に、安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。私たちは、かねてより安倍総理の立憲主義を無視した政治手法に危機感を覚え、断固、このような横暴を許さないという思いで民主党内に「平和と安定のための安全保障を考える連絡会」を立ち上げました。
これまで、海江田代表に対して集団的自衛権行使容認に反対し、民主党としての立場・対応姿勢を明確化することを申し入れるなどの活動を行ってきました。今後、この閣議決定の是非や、自衛隊法などの個別法の改正案が国会審議の俎上に上ってくることを念頭に、この問題に関する理論武装をしっかり行い、党内だけではなく広くこの問題に感心を持つ支援組織の皆さんと連携しながら、集団的自衛権を行使することがいかに大きなリスクを伴うものであるかということを国民の皆さんにわかりやすく情報提供していく目的で、勉強会を開催していくことにしたわけです。

第1回の勉強会では、東京新聞の半田滋論説兼編集委員から「安倍首相会見(7月1日)の問題点」について、大変明快にご講演をいただきました。内容の詳細は、フェイスブックに連絡会のページを立ち上げ、議事録を掲載していますので、ぜひそちらをご覧下さい。今後、集団的自衛権問題に関する情報もアップしていきますので、フェイスブックを利用しておられる方は、ぜひ連絡会のページをいいね!してフォローいただければと思います。あっ、ついでに、石橋みちひろのページにもいいね!して下さいね(^-^)v
7月5日(土曜日)の午後、東京の墨田区曳舟で、あべきみこ墨田区議の区政報告会が開催されたので、私も参加してきました。

あべ区議は、私と出身・支援組織が同じなのです。すでに3期11年、区議会で活躍されていますので、政治家としても大先輩。私の最初の選挙の時も、色々とアドバイスをいただきました。
今日の区政報告会には、普段からあべ区議を応援して下さっている支援者の皆さんが多数駆け付けて下さって、用意した席が足らなくなるほど。まさに、嬉しい悲鳴です。地元で地道に活動し、実績を積み上げているあべ区議の活動の成果ですね。

会場には、来賓として、山崎昇墨田区長も応援に駆け付けて下さって、激励のご挨拶を述べていただきました。そして私も、国政報告を兼ねて連帯の挨拶をさせていただいて、(1)国政では、今、区民の皆さんのこれからの暮らしに大きな影響を与える重要な議論が行われているので、ぜひあべ区議を通じて皆さんの声を私たちにも届けて欲しい、(2)多くの課題の中でも、やはり、景気回復を実現するためにも、そして社会保障を支えていくためにも、働く者の雇用の安定と安心をいかに確保するかが重要だが、残念ながら安倍政権は、雇用規制の緩和を進めようとしていて、それではむしろ雇用が一層、不安定で不条理なものになってしまう、(3)そして何と言っても、子どもたちのためにも平和な国を守っていくことが重要だが、安倍政権は憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を容認しようとしており、それは立憲主義、法治主義、民主主義を守る観点から決して認めてはいけない、という内容で挨拶をさせていただきました。

さらにこの国政報告会には、すばらしい応援団が駆け付けてくれたんです。鈴木あやこ江東区議と、本目さよ台東区議です! お二人も、出身・支援組織が同じで、私たちにとっては後輩にあたります。会合では、二人で交代しながら司会進行役を務めてくれたのですが、素晴らしい進行をしてくれて、本当に頼もしく感じました。区議になって3年、成長してくれています。
あべ区議とはこれからもしっかりと連携していきたいと思いますし、鈴木区議、本目区議も含め、みんなで力を合わせて応援して下さっている皆さんのご期待に応えられるよう、頑張っていきます!
今日(7月4日)、来日中のヤン・ニーセン博士と民主党「多文化共生議連」役員との意見交換を行いました。テーマは「移民統合政策」です。

欧州では、2000年代以降、「移民統合」が各国の主要な政策課題となったため、その分析を行うための様々な指標が開発されてきたとのこと。その中で、二つの重要な指標があって、一つが「統合政策(法制度レベルでいかに移民統合が進展・確保されているか)」に関する指標として開発された『MIPEX』、もう一つが、統合政策の成果(実態としてどの程度、移民統合が進展・確保されているか)を計るためにEUとOECDがそれぞれ開発してきた「成果指標」です。
これらの指標を用いることで、各国において、国外からの移民がどれだけ、社会的・経済的・政治的な統合(差別解消)を確保されているかを計り、国際比較を行い、自国の政策の再検討・改善を図ることができるというわけです。 また、MIPEXと成果指標とのギャップを分析することで、政策と現実との乖離をあぶり出し、その解決策を検討することも可能とのことです。
今日、お話しを伺ったニーセン博士は、欧州のMigration Policy Group (MPG)の所長さん。MPGは、欧州を代表する移民政策のシンクタンク(ブリュッセル)だそうで、MIPEXを開発したのがこのMPGです。今日、ニーセン教授に同行していただいた明治大学の山脇教授らが、このMIPEXを使って日本の移民統合の状況についても分析をされていますが、現状、かなりお寒い結果。
まさにこの辺が、私たち多文化共生議連で問題意識を持って議論をしていく課題なので、今日はいい意見交換となりました。なお、英語のサイトですが、MIPEXについてはこちらに詳細が説明されていますのでご参照下さい。
今日、7月1日は、私の49回目の誕生日でした。お祝いのメッセージをいただいた皆さん、ありがとうございました!
7月1日は私の49回目の誕生日でした。お祝いのメッセージをいただいた皆さん、ありがとうございました。


チーム石橋のスタッフから、お祝いとケーキを贈ってもらいました。お祝いは、通常国会の本会議で代表質問した時の写真パネルと、島根の銘酒「王禄」でした。嬉しい~! 日本酒好きの皆さん、王禄はいいです。ぜひお試し下さい!
さて、そんな素晴らしい誕生日・・・のはずだったのですが・・・今日は、違う意味で忘れられない、忘れてはいけない誕生日になってしまいました。
すでに皆さんもご存じの通り、本日、安倍政権は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定しました。暴挙としか言いようがありません。政治的クーデターとも言える蛮行です。まるで悪夢を見ているようで、強い憤りを感じます。
安倍総理は、今日の記者会見で、「国民の命を守る」と繰り返し述べています。しかし、安倍総理の記者会見は、欺瞞に満ちたものでした。「自民・公明の連立与党が濃密な協議を積み重ねてきた結果だ」と言いますが、それはつまり、国民的な議論は一切無しに、国会での議論も一切無しに、連立与党の・・・しかもその一部の代表者たちだけが、密室で、まるでゲームのように言葉遊びをして仕上げた結果で、憲法9条を捨て去ってしまったことを認めているに過ぎません。安倍総理の全く私的な懇談会が、結論ありきの報告書を提出してまだ1ヶ月余り。何が濃密な協議なのでしょうか?
安倍総理は「集団的自衛権が現行憲法の下で認められるのかという抽象的・観念的な議論ではない。現実に起こりえる事態に現行憲法の下で何をなすべきかという議論だ」と言っていますが、『集団的自衛権は現行憲法下では認められない。認めるためには憲法を改正するしかない』という事実は、抽象的・観念的な議論ではなく、それこそ長年の自民党政権下で国会での濃密な審議を経て積み上げられてきた結果としての確立された解釈です。
現実に起こりえない事態、個別的自衛権または警察権の範囲で対応可能な事態を、あたかも集団的自衛権を行使できなければ対応できない事態かのように国民を欺いて、現行憲法下でできない武力行使に道を開こうとする議論に過ぎません。
安倍総理の今日の記者会見、そして閣議決定がなぜ欺瞞かと言えば、それが、今回の問題の本質に全く触れていない、つまり、解釈改憲による集団的家意見の行使容認が何を意味するのかを敢えて隠そうとしているからです。
安倍総理は、(1)ときの政権が勝手に憲法解釈を変更して、平和主義、立憲主義、法治主義、民主主義を破壊してしまうことの危険性、(2)日本が攻撃を受けていないにもかかわらず(つまり日本が当事国でないにもかかわらず)、国外で他国の戦争・紛争に介入して武力行使することで生じる危険性(つまり日本国民がかえって無用の攻撃に曝されるリスク)、(3)自衛隊が他国の戦争・紛争に武力を持って介入することで、日本の若者が戦死する(相手を戦死させる)危険性、(4)専守防衛が崩れることで安全保障予算が増大していく危険性、(5)将来、本当の意味で国民を守るための自衛隊の要員が確保できなくなる危険性、などについて一切、説明していません。
架空の事例を使って感情に訴え、ナショナリズムを高揚し、リスクを隠して問題をすり替える・・・これは、昨年、麻生副総理がつい本音を喋ってしまったように、「ナチスの手口」を学んだ結果なのでしょうか? とすれば、その先に待っているのは一体どのような国なのでしょうか?
安倍政権は、そして自民党・公明党は、数の力で何でも出来ると奢っているとしか思えません。その奢りを正すのは、憲法の所有者であり、我が国の主権者である国民の力です。
今日が終わりではなく、今日をはじまりにしましょう。平和を守るための運動を、今日から始める・・・そのために、忘れてはいけない誕生日にしたいと思います!
6月27日(金)の夕方、私が育った故郷、島根県松江市で、国会議員になって初めての国政報告会を開催しました。金曜日の夜だったにもかかわらず、会場は用意した120席が満席に! 多くの方々にお集まりをいただいて、本当に感激しました。

そしてこの国政報告会には、私と同期の仲間が二人、応援に駆け付けてくれました。北海道選挙区の徳永エリ参議院議員と、千葉選挙区の小西洋之参議院議員です。二人とも、志を同じくする本当に信頼できる仲間で、政策の取り組みも色々と協力・連携しながら活動しています。
その同期二人の応援を受けて、国政報告会は二部構成で行いました。まず、第一部が国政報告の部。最初に小西議員が、「安倍政権の解釈改憲を斬る!」と題して、憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使容認がいかに危険なものかを分かりやすく解説してくれました。続いて徳永議員が、「政府与党の農業政策を斬る!」と題して、政府が進めようとしている農政改革が、いかに地方の、とりわけ中山間地の農業にとって危険な政策であるかをお話ししてくれました。
そして三番手が、私。今回は、「安倍政権の雇用規制緩和策を斬る!」と題して、昨年来、政府が進めている労働・雇用規制の緩和政策が、いかに労働者に悪影響を与え、翻って日本社会を疲弊させるかについて説明しました。

その後、第二部では、会場からいただいたご質問に私たちがお答えする形で進行。司会役は、地元で活躍している岩田ひろたか島根県会議員が務めてくれました。こちらも時間が限られていて、全ての質問にお答えすることは出来なかったのですが、色々と鋭いご質問をいただいて、いいやり取りをさせていただいたと思います。
そして最後の〆は、「島根から石橋みちひろ君を応援する会」の唐桶NTT労組島根分会長の閉会のご挨拶。会場に来ていただいた皆さんに、引き続き私たちの活動を応援することについて要請していただいて、満場の激励の拍手をいただいて閉会となりました。

あらためて、地元松江でも、多くの皆さんが温かく応援して下さっていることに感謝したいと思います。大きな力をいただきましたので、皆さんのご期待にしっかり応えていきます!
今日、6月27日(金)の午後6時から、私の故郷の島根県松江市で、国会議員になって初めての「国政報告会」を開催します。会場は御手船場町の労働会館4階会議室です。
いや〜、考えてみれば、やってなかったんですよ、国政報告会。私の場合、全国比例選出ですので、いつも全国各地の支援組織の皆さんのところへお邪魔して活動していますので、地元とは言え、島根で特別な活動をするっていうのはなかったんですね。でも、生まれ育った島根には、地元出身だからこそ応援して下さっている方々も少なからずおられますので、やはり一度、日頃の活動をご報告させていただくべきだろうと、今回の企画に至ったわけです。
そして、今日の報告会には、私の同期の仲間で、北海道選挙区の徳永エリ参議院議員、千葉選挙区の小西ひろゆき参議院議員が応援に駆け付けてくれます。ご両名は、私が最も信頼し、力と心を合わせて一緒に活動している仲間たちの代表格です。今日の報告会では、それぞれが今、最も力を入れて取り組んでいる分野で、徳永議員は「現政権の農業政策の問題点」、小西議員は「安倍政権が強行しようとする解釈改憲の危険性」について、分かりやすく解説してくれます。
そして私はと言えば、やはり、今、もっとも重要な課題である労働・雇用政策についてお話しします。まずは、本来とるべき政策を訴えつつ、それに反して安倍政権が強行しようとしている更なる雇用規制の緩和政策を徹底的に批判したいと思います。
地元松江の皆さん、ご近隣の皆さん、お時間あったらぜひご参加下さいね。とっても参考になる話、満載です! では、会場でお会いできるのを楽しみにしています!