6月1日付の当ブログ記事「どうしても『残業代ゼロ』を実現したいらしいが・・・」で、現在、政府の「産業競争力会議」で検討が進められている「残業代ゼロ制度」の問題点を指摘しました。その後も、民主党の厚生労働部門会議等で議論を進めているのですが、その中で政府が提出した資料や、われわれからの質問に対する回答に数々の疑問が出てきていますので、以下、続報としてお伝えしておきます。
安倍総理の記者会見
5月28日の第4回産業競争力会議の後、安倍総理は「新たな労働時間制度」に関して、以下のように述べたそうです:
=======================
働き手の数に制約がある中で、日本人の意欲と能力を最大限に引き出し、生産性の高い働き方ができるかどうかに、成長戦略の成否がかかっていると思います。あわせて、少子高齢化が進む中、子育てや介護などと仕事とをどう両立するかは、大きな課題であり、社会の発想を変えねばならないと思います。そのためには、働き手が十分才能を発揮し、各人の事情に応じて柔軟に働き方を選べるように、働き方の選択肢を増やすことが重要であります。
このため、成果で評価される自由な働き方にふさわしい、労働時間制度の新たな選択肢を示す必要があります。新たな選択肢については、「長時間労働を強いられる」あるいは「残業代がなくなって賃金が下がる」といった誤解もありますが、そのようなことは、絶対にあってはならないと考えます。まずは「働き過ぎ」防止のために法令遵守の取組強化を具体化することが、改革の前提となります。その上で、新たな選択肢は、
1.希望しない人には、適用しない。
2.職務の範囲が明確で高い職業能力を持つ人材に、対象を絞り込む。
3.働き方の選択によって賃金が減ることの無いように適正な処遇を確保する。
この3点の明確な前提の下に、検討していただきたいと思います。こうした限られた人以外の、時間で評価することがふさわしい、一般の勤労者の方々には、引き続き、現行の労働時間制度でしっかり頑張ってもらいたいと考えます。
=======================
ここで安倍総理は、「長時間労働を強いられる」「残業代がなくなって賃金が下がる」ことがあってはならないと明言していますが、さて、一体、どういう意味での発言でしょうか???
働き過ぎ防止のための法令遵守の取り組み強化?
ここで言う法令遵守の取り組み強化というのは、労働基準監督署の体制強化のことを言っているようです。このこと自体は、私が初当選以降、ずっと国会質問で取り上げてきたことですので、大歓迎ですし、今回のことに関係なく今すぐ実行に移すべきです。
ただ、前回の記事でも指摘しましたが、本来、「働き過ぎ防止」を言うのであれば、まず現在の労働時間規制では事実上、青天井になっている労働時間について、(1)残業時間を含めた年間(及び週、月単位でも)総実労働時間の上限規制の導入、(2)勤務間インターバル(休息時間)規制の導入、(3)1週間に1日の絶対週休の導入、をセットで導入する必要があります。いくら取締体制を強化しようが、36協定の特別条項を結んで合法的に過労死レベル以上の残業時間を設定できる状態を温存しては、違反にならないのだから効果はありません。
まず何より、この労働時間の上限規制について明確な方向性が示されなければ、「改革の前提」条件は整わないのです。
さらに、もし今回の制度改革が、対象となる労働者を労働基準法の労働時間規制の適用除外にする(=基準法違反をしても罪に問われない)という措置だとすると、これまた取締体制の強化では何の対策にもなりません。だって適用が除外になっているわけですから、違反しても取り締まれないわけです(苦笑)
具体的な制度設計はまだ分かりませんが、もし労働基準法の労働時間規制を適用除外にするという話であれば、労働基準監督制度の枠外に置かれてしまう可能性がある、ということは留意しておく必要があると思います。
希望しない人には適用しない?
これも前回触れましたが、「新たな制度は労働者本人の選択制で、希望しない人は現行制度のママだから大丈夫」と言われると、何となく「それならいいか」と思ってしまうかも知れません。しかし、この新たな制度を選択するかしないかで、処遇や労働時間に全く何も差がつかないのであれば、そもそもこの制度を導入する意味がないわけで、経営側の並々ならぬ意欲を感じ取れば、当然に選択の有無で処遇格差を付けてくるはずです。
加えて、対象となる労働者は、

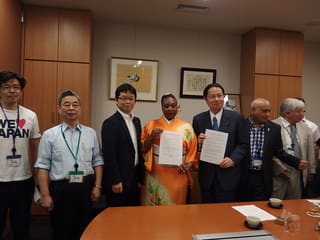




 石橋議員が明日の参議院文教科学委員会で質問にたつことが決まりましたのでお知らせいたします。
石橋議員が明日の参議院文教科学委員会で質問にたつことが決まりましたのでお知らせいたします。

 本日午後3時より党首討論が行われます。
本日午後3時より党首討論が行われます。


