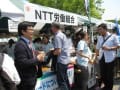皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしになりましたか? 私は、事前にお知らせしていた通り、ミャンマーに視察出張に行ってきました。昨年8月のカチン州訪問に続くミャンマー出張で、今回は、ミャンマーの東部、タイとの国境沿いに広がるカレン州をメインに行動してきました。
すでにこのブログでも何度かご紹介していますが、カチン州やカレン州を含むミャンマーの少数民族地域の多くは、長年に渡る国軍との武力闘争の結果、村々が破壊され、多くの住民が国内避難民(IDP)または国外難民として故郷を離れて生活しています。カレン州の場合は、2012年に政府との暫定停戦合意が締結されるまで、60年余りに渡って戦闘が続けられてきたため、難民の数も10万人以上と言われています。
2012年の暫定停戦合意によって、ひとまず大規模な戦闘は収まっていて、各地で町や村の再建に向けた取り組みが始まっています。特に、国際的な支援も受けながら難民の帰還支援に向けた取り組みが各地で始まっていて、日本もODAでその取り組みに貢献しているのです。
今回は、カレン州におけるその日本の帰還支援事業の実状を視察に行ったというわけです。以下、その概要を報告します。
《4月28日(月)》
前日午後、ヤンゴンに到着して、早速、在ヤンゴン日本大使館及びJICAヤンゴン事務所との意見交換を実施。そして翌朝8時から、ヤンゴンのカレン民族市民組織(NGO)の代表者たちとの意見交換を行いました。
私の最大の関心事は、市民運動の統一。これまでとかく「分裂している」とされてきたカレンのNGOグループですが、彼らによれば「2年前の暫定停戦合意以前は、国内で活動しているNGOと、タイ側を拠点に活動しているNGOとは、全くコミュニケーションを取ることが許されなかったし、出来なかった。会合が発覚したら投獄された。だから意思統一もできず、バラバラの活動を余儀なくされてきた」とのこと。暫定停戦合意によってようやく連携が可能となり、Karen Community-Base Peace Support Network (KCBPSN)という新たなネットワーク組織を結成して、今、このKCBPSNを窓口に海外支援組織との連携を強化しているとのことでした。この点はまず歓迎したいし、彼らの努力に敬意を払いたいですね。
その上で、彼らの懸念は、「日本のODA支援はミャンマー政府との協議のみで実施されていて、民族組織側と全く連携がない」という部分。この点は、私たちもかねてから問題として指摘しているところです。「米国大使館も英国大使館も私たちを招いて協議してくれるのに、日本大使館やJICAからは声がかかったことがない」と。今、JICAがカレン州(とモン州)で基礎調査を行っている難民帰還支援プロジェクトについても、「その対象となるカレン民族の話を聞かずして、いかなるプロジェクトをやるつもりなのか?」と心配していました。これらの点は、今回の視察でカレン民族側組織から異口同音に発せられた心配の声ですので、私としてもフォローしていきたいと思います。

会合終了後、ヤンゴンからカレン州パアンへ車で移動。約5時間半の行程でした。ヤンゴンを出ると、風景はもう田園か野原ばかり。素朴な田舎の風景と、時折通過する町々の様子を興味深く眺めながら、意外にあっという間にパアンに到着しました。
パアン到着後、そのままカレン州の州庁舎に行って、カレン州知事と会談。会合にはずらっと役人の皆さんが並んだ(下の写真。これがミャンマーの典型的な公式会合の様子です)のですが、話をするのはもっぱら州知事だけ。「気むずかしい人」と聞いていたので、かなり慎重に言葉を選びながらの会談でしたが、最後の方は州知事から日本の現状について質問が出されるなど、最後までいい雰囲気でした。
私が特に要請したかったのは、現在、政府側の管轄下にある地域に限定されている日本のNGOの活動範囲を、今後、カレン民族組織側の管轄地域や、双方の影響が及ぶ中間地域にも拡大させて欲しいという点。それをかなりマイルドに表現して、以下のようにお話ししました:
「日本国民からの支援を、ぜひ、真に支援を必要としているカレン州内の地域や住民たちに届けていきたい。そのためには、様々なチャンネルで相互に連携・協力し、ニーズと支援をマッチングさせ、必要な支援を必要な地域に届けられるようにしていく必要があり、政府間だけでなく、民間NGO間や、コミュニティー間での連携強化が必要と考える。昨年から、日本のNGOがカレン州で支援を始め、頑張ってくれているが、今後、支援を必要とするカレンの市民組織や地域、コミュニティーとの連携を広げ、より幅広くカレン州の再建に貢献できるよう、州政府としてもサポートして欲しい」
州知事は、それでも慎重な言い回しの回答でしたが、「日本の支援には大いに感謝し、期待している。カレンの複雑な事情を理解してもらうことが第一で、その上で、必要な協力・連携をしていきたい」との言葉がありました。今後、継続的に働きかけを続けて行くことで、より望ましい形の支援が(徐々にではあれ)展開していけるのではないかと期待しています。

州庁舎を離れ、今度は日本のNGOグループの皆さんとの会合へ。昨年からスタートしたカレン州で帰還支援プロジェクト事業を担ってくれているNGOの皆さんが集まってくれました。
このNGOグループによる事業は、NGOのネットワーク組織であるジャパンプラットフォーム(JPF)を窓口に、その傘下のNGOがそれぞれの得意領域で事業を受け持って、カレン州内の村々で社会インフラの再構築や生活再建支援を行っているものです。この最初の会合では、それぞれのNGOから事業の概要やこれまでの成果、さらには今後の展開についての展望など、お話しを聞かせていただきました。それぞれの事業が大変興味深い内容で、私もついつい質問攻めにしてしまいましたが、多くの有益な情報をいただきました。

会談を終えて外に出ると、もう辺りは真っ暗。そのまま近くのBHNテレコム協議会さんの事務所にお邪魔して、事務所内の様子をパチリ。専門家の方は、このオフィスに寝泊まりをされていて、寝室(?)も見せていただきました。頑張っておられます。

《4月29日(火)》
翌朝、8時半にパアンのホテルを出発。BHNテレコム支援協議会とピース・ウィンズ・ジャパン(PWJ)がプロジェクトを実施している、北東部のラインブエ・タウンシップに向かいました。
BHNのプロジェクトサイトは、Shanywathit(シャインワティ)という、ラインブエ・タウンシップの中でも北東部の端、タイとの国境にほど近い小さな村です。はじめ、車で3時間以上かかると言われていたのですが、新しい道路が急速に整備されてきていて、結果、今回は2時間少々で到着しました。しかし道中、至る所に橋のない川があって、なかなかスリルのある道のりでした。これでは雨期には通行できないでしょうね。

途中の景色はこんな感じ。素朴な雰囲気ですが、つい2年前まで実際に戦闘が行われていた地域も含まれています。


そして到着したShanywathit(シャインワティ)。早速、BHNが設置した太陽光発電システムを見せてもらいました。村の集会場には、LED電球や、大画面テレビ、そしてCDMAシステムの電話機などが設置。これらのおかげで、村人たちが毎日のように集会場にやってくるので、村内のコミュニケーションが良くなったとお坊さんも村のリーダーも大変喜んでおられました。(BHNの活動についてはこちらもご覧下さい)





そして、この集会場の裏手にピースウィンズジャパンの支援で建設中の井戸も視察。カレン州でも、とにかく安全な水を安定的に確保することが大変で、この水の問題の解決なくしては生活再建も将来的な難民の帰還もままなりません。しかし井戸というのも、ただ掘ればいいというわけではないので、井戸の修理や新設は非常にニーズの高い支援事業とのことでした。こちらはまだ建設中ですが、皆さん、完成が待ち遠しいと!

午後になって、シャインワティから、ピースウィンズジャパンが支援事業を行っている別の村へ移動。道中で、ある村の食堂に立ち寄ってみんなで地元料理でお昼ご飯。どこでも何でも食べられるっていうのは、こういう時に強いですね(笑) いや、本当に地元料理って美味しいです。


そして、次なる村に到着すると、学校では子どもたちが伝統舞踊の練習中。しばし、綺麗な踊りを見させてもらいました(ちなみに、写真の左側の女子生徒たちと、右側の生徒たちは違う踊りを練習しています。双方が音楽をガンガン鳴らしながらの練習で、よく混乱しないなと感心・・・笑)

そして到着したのがこの井戸。元々あった井戸ですが、PWJの支援で全面的に改修され、足こぎ式のポンプも設置されて村人たちが大喜び。私も思わずトライさせてもらったのですが、実に軽くてスムーズで、これなら子どもでもお年寄りでお難なく水を汲み上げることが出来ると実感しました。


そして、その場にいた村人たちと談笑。これぞ、井戸端会議(笑) 井戸の話だけでなく、村での日々の生活や、戦闘が行われていた頃の話、子どもたちの教育や将来のことなど、つい時間を忘れて話し込んでしまいました。楽しかった! (ピースウィンズジャパンの活動についてはこちらを参考にして下さい)

《4月30日(水)》
パアンでの3日目、実質的に最終日となるこの日は、まずカレン民族側のNGOグループの皆さんとの会合からスタートしました。すでに4月28日にヤンゴンで会合していたので、予備情報はタップリ。私からも色々と質問をさせていただきながら会合を進めて行きました。
NGOグループ側からは様々な質問や意見提起があったのですが、まず何と言っても、日本のNGOがカレン州内でさまざまなプロジェクトを実施していることについて私が尋ねると、彼らは「知らない」「全く情報がない」「何の相談も説明もなかった」という反応。私がその背景と理由を説明したのですが、「わたしたちの州で日本のNGOが活動しているのに、私たちが全く何も知らないというのはどうなのか?」と繰り返し訴えられました。
結局、ヤンゴンでの会合と同様に、「欧米の国々やNGOは私たちと相談して事業を進めてくれているが、日本はどうして出来ないのか?」というところに行き着いてしまいます。「日本のNGOたちはぜひそうしたいと思っているし、実際、すでにそうしているNGOも一部ある。今後、徐々にではあるが、対話が広がっていくように私の立場からも努力したい」とお伝えしました。やはり、この辺が大きな課題です。

NGOの皆さんとの会合に続いて、カレン民族同盟(KNO)のパアン事務所へ。この会合には、KNOの拠点があるタイ側のメソトから、KNUの国際局長や民生局長がわざわざやってきてくれました。
会合では、最近のKNUの動き、特にカレン州の再建に向けた取り組みの話や、政府との和平交渉の状況、さらにはKNUをはじめとするカレン民族側の複数の組織が進めているネットワークづくりの話など、さまざまにお話しを伺うことができました。特に、「これまで確かにKNUも、カレン民族側の組織も分裂していて、海外のドナーには複雑かつ難しい印象を与えてきたと思う。そのことについて我々自身も問題意識を持っており、KNUとしても組織外対応の一元化や他の民族組織との連携強化を進めている」との発言があったことは、いい意味で驚きましたし、その自主的な取り組みを歓迎したいと思います。


会合の後、パアンの市内で、現地の皆さんが普通に食事する道ばたの食堂でお昼ご飯。これで(下の写真)1人100円以下。それでも地元の皆さんにとっては安くない外食のお昼ご飯です。


さて、昼食後、またしても車で北東部の村へ。午前中に会合したカレンNGOの皆さんに、「普通の村で村人たちとじっくり意見交換をしたい」とお願いしたら、連れてってくれました、普通の村に。で、集めてくれました、村人たちを!


上の写真のような調子で、約2時間。内戦の話から政治の話、そしてまた子どもたちの教育の話やカレン州の将来の話まで、いろんな話をああでもない、こうでもないと言いながらじっくり話し合いました。しばしば、村人たちが自分たちの間で議論になって盛り上がってたのが印象的でした。
そして、パアンへの帰路で素晴らしい夕日と遭遇。写真ではなかなか伝わらないと思いますが、実に綺麗な真っ赤な夕日でした。

パアンに帰り着いたのはもう夜。さすがに疲れたし面倒くさいので、宿泊ホテルのレストランで夕食を済ませようと思ったら、ばったり遭遇したのが帰還支援プロジェクトを実施しているNGOの一つ、日本国際民間協力会(nicco)の皆さん。せっかくだから(?)と勝手に合流して、一緒に夕食をとりながら現地での苦労話など、さまざまにお話しを聞かせていただきました。それにしても、お三方とも、昨年暮れからパアンに駐在してプロジェクトを実施しておられます。何ともたくましいし、頼もしい! (niccoの現地活動についてはこちらを参照して下さい)
毎日停電があったり、これから雨期に入ったりで本当に大変だと思いますが、引き続き、日本国民とミャンマー国民(カレンの皆さん)をつなぐ架け橋として頑張って下さいね!

ということで、長くなりましたが、ミャンマー視察報告の第一弾、カレン州での活動部分、これで終了です。この後、ヤンゴンでの活動についてはまた続きで報告しますので、しばらくお待ちを!